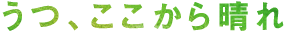- トップ
- うつ病患者さんを⽀える⽅へ
- 救われた言葉、傷ついた言葉
救われた言葉、傷ついた言葉
一緒にはたらく仲間がうつ病を患ったとき、それを周りで支える方は、どのような言葉をかけたり、
どのような態度で接すれば良いのかわからないこともあるでしょう。
また、いままでかけてきた言葉や、これまでの態度が間違っていることもあるかもしれません。
患者さんとの、よりよいコミュニケーション方法を探っていきましょう。
1“元気がないね、大丈夫?„
“心配だ、何かできることない?„
(治療初期において)

言ってはいけません。
治療初期の段階では、どんな言葉でも患者さんのストレスになる可能性があります。
「今日はすっきり起きられたね」などと生活習慣が安定してきたことを患者さんに伝えるなど、ほどよくほめる程度にとどめましょう。
大げさにほめたり、心配することも患者さんにとってストレスになることがあります。そのため、特に治療初期においては、様子をみながら話しかけるなど、生活を見守る程度のコミュニケーションにしましょう。一方で、ある程度回復して外出や趣味への意欲があらわれ、冷静な判断ができるようになってくれば、やさしく背中を押してあげるような言葉やサポートが、患者さんの支えになります1)。
2“生きてほしい„
(自殺をほのめかされたとき)

言ってあげてください。
うつ病の症状のひとつに自殺願望があります。
患者さんから「もう死にたい」など、自殺をほのめかすような言動がみられたら、しっかりと耳を傾け「死なないでほしい」、「あなたが大切だ」と伝えてください。
また、「死にたいと言う人は、実際には自殺しない」、「本当に自殺するときは何も言わない」というのは根拠のない決めつけであり、うつ病の患者さんが死をほのめかす言動をとった場合は、自殺の危険性があるのだと考えてください1)。
また、話半分に聞くことや、説教口調でなだめたりすると、患者さんが自分のつらい感情を否定されたと失望し、自殺を試みてしまうことがあります。このような場合は、本人の話に耳を傾け「~と思うんだね」と言葉をそえてください。または、黙ってよりそうだけでもかまいません1)。
3“なるべく早く、また稼げるように
なってほしい„(休職初期)

言ってはいけません。
休職の初期に、経済的な話をすることは避けましょう。
患者さんの不安や心配は、症状の悪化や治療妨げの原因となる可能性があり、回復が遅れることで経済的な問題をより深刻化させることにつながります。
医療費や生活費などの経済的な不安がある場合は、各種公的な制度を活用することで負担を軽減できる可能性があるので、調べてみましょう1)。(支える制度)
もし制度の利用についてわからないことがあれば、地域の役所や精神保健福祉センター、医療機関の精神科ソーシャルワーカーなど補償制度に詳しい専門家に相談してみましょう。
また、うつ病の症状が回復すれば、患者さんと経済的な話をできるようになります。外出や冷静な判断ができるような活動性がみられるようになったころに、相談を試みると良いでしょう。その際、医師などの医療従事者を交えて話すことをおすすめします1)。
4“支える側も大変なんだ„
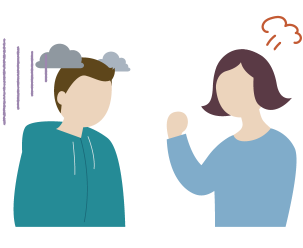
言ってはいけません。
患者さんに対して愚痴を言うことは避けましょう。患者さんの新たな悩みとなる可能性があります。
たとえ、患者さんには関係のない話題であっても、愚痴は患者さんのストレスになる可能性があるため、患者さんを支える方は患者さんに対して聞き役に徹することが大切です。
ただし、患者さんを支える方が不満を隠して明るくふるまうことや、不満をすべてため込むことは、患者さんを支えるうえで大きな負担になります。
患者さんの継続的なサポートのためにも、患者さんを支える方は、第三者に相談することが望ましいでしょう。その際、親しい方に相談することが難しい場合は、医師や臨床心理士、カウンセラー、精神科ソーシャルワーカーなどのうつ病の専門家への相談や、各種相談窓口を利用することができます1)。
5“その仕事大変でしょう
こっちでやっちゃうよ„

言ってはいけません。
復帰後の患者さんを特別扱いすることは、患者さん本人だけでなく、周りの人たちにも悪影響を与えることがあります。
特に職場においては、過剰な配慮や特別扱いをすると、他の社員が反感を抱く可能性があり、患者さんもはれもの扱いされることで不快な思いをすることがあります。
患者さんの相談にのり、サポートすることは大切なことですが、職場の秩序を守ることも重要です1)。
6“間に合うように
自分で調整してね„
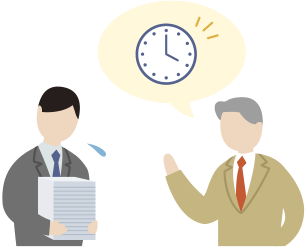
言ってはいけません。
うつ病の患者さんに対して、会社側がいっさい配慮をしない対応をするのは問題です。
たとえば、勤務時間内に終わらない量の作業を任せておきながらその調整を本人に任せたり、他の社員と比較したり、さらに患者さんに責任を押し付けることは、患者さんに無理を強いて、不快な思いをさせているだけです1)。
企業には安全配慮義務があり、労務管理の責任があります。本来、業務量の調整は企業が行うものです。しかし、大企業ではない限り、企業によって対応力が異なることは事実です。
企業として患者さんをサポートする姿勢が重要であり、少なくとも規定の範囲内で配慮することが求められます。したがって、患者さんの調整力不足を非難したり、企業側が調整を怠っている場合は、法的な問題となる可能性があります1)。
7“いつまで休職するのか
チームで共有させてください„

言ってあげてください。
患者さんが休職する際、診断書の内容と医師の治療方針を確認したうえで、休職から復職までのプロセスを共有しましょう。
また、その際に社内の関係者にも休職のプロセスを伝えることで、不足する人材の確保などの社内体制を関係者が調整しやすくなり、患者さんが休職することに対する関係者の不安や負担の軽減につながります。また、休職のプロセスを患者さんと共有することは、一見患者さんにプレッシャーをかけるように思えますが、実は積極的な治療につながります1)。
ただし、診断書に休職期間が書かれているにも関わらず、「1ヵ月で復職するように」などと不要な圧力をかけたり、「戦力としてみていない」と否定的な意見を述べたりすることは厳禁です1)。
8“これまでどおりバリバリ働いていただきます„
(復職当初)

言ってはいけません。
復職当初から休職前のパフォーマンスを求めることは避けましょう。
患者さんは「健康になって戻る」のではなく、「働けるようになって戻る」こと3)を前提に治療に取り組んでいるからです。患者さんとの話し合いを重ねたうえで、ブランクを補うための準備期間を組み込んだ復職プランを立て、段階を踏んだ復職を計画しましょう1)。
復帰プラン

- 適
応
期 - 復帰から3ヶ月目まで。通勤するだけでも精一杯の時期。単純な作業や手伝いなどからはじめてもらい、まずは会社に通う習慣をとり戻してもらう。
- 回
復
期 - 4ヶ月目から6ヶ月目まで。通勤には慣れ、一定の業務はこなせるように。本人も周囲も期待が高まるが、まだ無理をしすぎないように、業務量を調整する。
- 安
定
期 - 7ヶ月目以降。状態が安定して、業務が元の水準まで高まってくる。残業も可能に。ただし、以前とまったく同じ仕事を任せると再発する可能性があるため、業務の調整をしたほうがよい。
<判断基準の例>
- ・労働者が十分な意欲を示している
- ・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる
- ・決まった勤務日、時間に継続して就労できる
- ・業務に必要な作業ができる
- ・作業による疲労が翌日までに十分回復する
- ・適切な睡眠覚醒リズムが整っている、昼間に眠気がない
- ・業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している
- など
9 “ご主人の休職期間が予定より長引いていますが、家庭内での調子はどうですか?„
(本人ではなく、奥さんに直接連絡をしたとき)
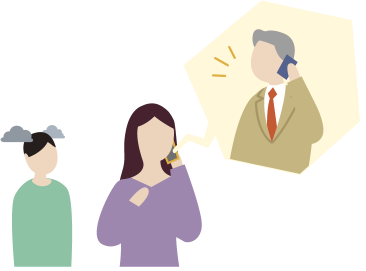
言ってはいけません。
患者さんを介さずに、直接ご家族の方に状況を尋ねるのは避けましょう。
うつ病による休職期間が長引いた場合など「本人に聞いてもわからない」と勝手な判断で、直接ご家族の方と連絡をとることはトラブルに発展する可能性があります。
職場と患者さんとの信頼関係を維持し、家族間の不和を引き起こさないためにも、まずは本人と直接連絡をとりましょう。
どうしても連絡がとれない場合は、「〇〇日までに返信がなければ、確認のためにご家族に連絡します」と伝えるなど、細かい配慮が必要です。
ただし、自殺をほのめかす言動などに気づいた場合は、家族や医師へ連絡するなど、安全性を優先した対応をとりましょう1)。
- 1)有馬秀晃 監修:うつ病の人に言っていいこと・いけないこと, 講談社, 東京, 2014
- 2)山本晴義 監修:図解やさしくわかる うつ病からの職場復帰, ナツメ社, 東京, 2015
- 3)厚生労働省:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~, 平成25年11月
うつ病患者さんをサポートするための具体的なポイントは、以下よりご覧ください。