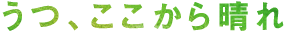- トップ
- うつ病と診断された方へ
- うつ病と生活|周囲の人々とのかかわりかた
周囲の人々との関わりかた
「周囲の人々」には、家族や友人、親類、職場の上司や同僚など、さまざまな人が当てはまります。
険悪な人間関係がうつ症状の引き金となることもあれば、良い人間関係がストレスから心を守ってくれることもあるでしょう1)。
ここでは、うつ病と向き合っている方向けに、人付き合いのヒントになる考え方をご紹介します。
- うつ病になると、人間関係はどうなる?
-
うつ状態が長引くにつれ、人間関係は希薄になりがちです。なぜなら、うつ病の症状により人付き合いをする気力・体力がわかず、自信もなくし、仲が良かった人たちでも疎遠になっていくからです1)。ただ、これはうつ病の症状が原因です。うつ症状が回復してくれば、また会うこともできます。
- うつ病と診断された直後は、どのようにすればいいの?
-
うつ病と診断された直後(急性期)は、気力・体力がかなり落ちている時期だと考えられます。まず、休みましょう。「人と会いたい」と思えるまでは、焦らず無理せず、心身を休ませることを優先してください。
- うつ病で困っているとき、誰を頼ればいい?
-
「メランコリー型うつ病(典型的なうつ病)」の特徴として、真面目で几帳面なタイプの人がなりやすいとされ2)、「自分だけで頑張らろうとしない、人の助けを借りる」ことが大切になります3)。
まずは主治医やカウンセラーに「自分の症状や生活環境での困りごと・悩みごとを誰かに話したい」と伝えて相談してみましょう。これまでの経験から、さまざまなアドバイスをもらえるはずです。
また、うつ病になって困っていた時に助けてくれた・支えてくれた人がいたら、その人を頼るのも良いでしょう3)。家族かもしれませんし、友人かもしれません。うつ病から回復して社会復帰しているのであれば、復職のときに助けてくれた人も頼ることができるかもしれません3)。
つまり、困ったときに話せる・信頼できる・寄り添ってくれる相手が誰なのか、整理しておくことが大切です3)。
- 人間関係は、うつ病の治療にもつながることなの?1)
-
はい。現在の人間関係に注目して治療していく対人関係療法があります。
うつ病を発症する原因は1つではありませんが(うつ病の原因)、家庭内・職場・学校などにおける人間関係のストレスは大きな発症要因になりえます。
対人関係療法は、例えば、当事者と関係が近く、当事者の心にも影響力のある人たち(重要な他者;親、恋人、親友など)との関係を振り返り、うつ病と強い関係がありそうな問題点をみつけて介入・治療していきます。
また、上手くいった/いかなかった人間関係のパターンを振り返り、その理由を探りながら次の関係構築に活かすことも、対人関係療法の考え方に含まれます。対人関係療法は専門家(医師や臨床心理士など)の手を借りて進めていく治療ですが、上手くいった人間関係のパターンを振り返って今後に活かす手法は、普段の生活でも応用できるかもしれません。
【出典】
- 1)水島広子:対人関係療法でなおすうつ病 病気の理解から対処法、ケアのポイントまで. 創元社, 大阪, 2019
- 2)野村総一郎 監修:健康ライブラリー 名医が答える!うつ病 治療大全. 講談社, 東京, 2022
- 3)神庭重信 監修:こころのお医者さんに聞いてみよう 「うつ病」の再発を防ぐ本 家族と本人が知っておくべき予防法. 大和出版, 東京, 2023