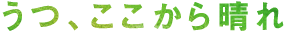- トップ
- うつ病と診断された方へ
- うつ病と生活|仕事のこと
仕事のこと
より前向きにうつ病治療と向き合うため、仕事とうつ病治療とのよいバランスを保つ必要があります。
ここでは、どのように仕事(一部家事を含む)とうつ病治療のバランスをとればよいのかをQ&Aで紹介します。
より前向きにうつ病治療と向き合うため、仕事とうつ病治療とのよいバランスを保つ必要があります。
ここでは、どのように仕事(一部家事を含む)とうつ病治療のバランスをとればよいのかをQ&Aで紹介します。
うつ病になったら
- 病気になったときの支援制度は?
-
さまざまな支援制度があるので、確認してみましょう。(保障・復職支援)
企業に勤めている場合、職場の休職制度や労災補償、傷病手当などを活用することで、収入がゼロになることを避けられます。
もし制度の利用についてわからないことがあれば、地域の役所や精神福祉保健センター、医療機関の精神科ソーシャルワーカーなど、補償制度に詳しい専門家に相談してみましょう1)。(相談先)補償制度を活用することで、
休職中の収入がゼロになることを避けられます
- 休養・休職を勧められないこともあるの?
-
うつ病の状態を診察したうえで、休養により生活リズムが崩れることで、うつ病が悪化するリスクが考えられる場合は、休養せずに治療を行うことがあります2)。
また、うつ病が軽度な場合、医師がうつ病の状態や就業状況、職場環境、患者さんの性格などから総合的に判断し、治療方針を決定します3)。その際、医師が休養や休職の判断を行うため、ご自身の希望とは異なる場合があります。
- 休職に必要なものは?
-
休職に必要なものは診断書です。
休職の手続きは、上司や人事を介して行います。その際、診断書を提出する必要があります。また、休職中の連絡先や会社の連絡窓口を決めておく必要があります。休職のために使用する休暇制度の期間や傷病手当、労災などの保障制度についても相談しておきましょう2、4)。 上司や人事と、休職するための面談を行う場合、医学的な説明が難しいと感じたら医師に相談しましょう2)。また、医師から休職が必要と診断された1~3日以内には会社を休めるように調整しましょう4)。このとき、無理して仕事を続けてしまうと、症状が悪化したり、回復が遅れることがあるため、仕事の引継ぎを最小限に抑え、無理せず速やかに休むことが大切です2、4)。休職までの流れ

休職相談シート
休職する際に、診断書と一緒に提出することで、休職の手続きを円滑にするためのシートです。
「PDFのダウンロード」ボタンを押して、PDFの保存・印刷をしてください。
印刷した「休職等相談シート」に氏名、提出日、提出先、休職スタート日、休職中の連絡先、緊急連絡先を記入してください。
また、休職の面談の際に、ご自身が会社へ連絡する場合に必要な各種連絡先や、休職のために利用する制度とその制度を利用できる期間を、職場の人に記入していただきましょう。

監修:渡邊衡一郎(杏林大学医学部 精神神経科学教室 教授)渡部芳德(医療法人社団慈泉会 市ヶ谷ひもろぎクリニック 理事長)
難波克行 著:うつ病・メンタルヘルス不調 職場復帰サポートブック, NextPublishing Authors Press, 2017
- 重大な決断はいつしたらいい?
-
重大な決断は回復してからにしましょう。
うつ病の症状の1つに判断力や思考力、集中力の低下があり、正常な判断ができない場合があります。また、抑うつ症状から考え方が悲観的になっている場合もあります1)。
そのため、重大な決断は、症状が改善されるまで先送りにするのが賢明です。決してご自身だけで決断せず、医師や家族に相談しましょう。また、判断を急ぐ場合は、家族に判断してもらいましょう1)。
休養・休職時について
- 休養・休職時にすることは?
-
休養・休職時は、仕事の内容に関する連絡はできるだけ避けてください。しかし、体調や状況については月に1回程度職場に連絡するようにしましょう。そうすることで、あせりや不安などと、復職への意欲とのバランスをとっていくことができます2、4)。
- 休養・休職時、自宅にいても家事のことが気になってしまい、気が休まらない。
そんなときはどうすればいいの?? -
医師から休養が必要と判断された場合は、何もしないように心がけ、十分に休養をとってください。
家庭内での家事などを任されている場合は、休養中でも気が休まらないことがあるかもしれません。その場合は、休養が優先すべきことだと考え、周囲にサポートを求めましょう。しかし、自宅での休養が難しい場合は、入院するという方法もあります7)。
復職について
- 復職の目安は?
-
以下が復職できる目安(判断基準)とされています8)。
<判断基準の例>
- 労働者が十分な意欲を示している
- 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる
- 決まった勤務日、時間に継続して就労できる
- 業務に必要な作業ができる
- 作業による疲労が翌⽇までに⼗分回復する
- 昼間に眠気がない
- 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している
など
- 復職するときに必要なことは?
-
回復期(うつ病治療中の過ごしかた)、つまり復職する前の期間では、少しずつ生活リズムを整えていきましょう9)。
生活リズムの調整に際して、何時にどのような活動(起床、食事など)をしたのか記録する「生活記録表」をつけると、自分の生活リズムがより把握しやすくなります(図)2)。
回復とともに生活への意欲もわいてくると思います。しかし、あせってうつ病発症前の生活リズムに戻すと悪化する可能性があるため、気をつけましょう。
外出や運動ができるようになってきたら、医師と相談して復職支援(リワーク)プログラムを活用してみるのもよいかもしれません2)。また、料理などの家事や通勤訓練、仕事に関する作業や勉強なども、この時期には実践しても構わないと考えられるので、医師に相談してみましょう10)。
医師が本格的に復職できると判断した場合、職場の人と面談の場を設け、復職について相談しましょう。また、それまでに復職支援プログラムを受けていれば、面談前にそのことを職場の人へ伝えておくと、話がスムーズに進むでしょう。面談の場では、自分の希望を伝え、復職予定日や試し勤務、復職プランなどについて話し合いましょう2)。図:生活記録表(例)

- 復職後、再発して再休職しないためには?
-
再休職を防ぐためには、復職前の休職のきっかけとなった原因を探し、対策を立てることが重要です。
復職後に仕事で無理をしてしまい、多くの患者さんがうつ病を再発し、再休職しています。
これは、休職前と同じ仕事を担当し、同じようなストレスを抱えることが、再発の原因となることを認識できていないことが原因としてあげられます11)。
再発による再休職を防ぐための支援制度として、復職支援(リワーク)プログラムがあります。このプログラムは医療機関のほかに、精神保健福祉センターのような公的機関や、NPO法人などの施設でも実施しています2)。
復職支援プログラムを受ける場合、復職の準備をしていることを職場の人に伝えましょう。職場の人に復帰の見通しを伝えることで、復帰への不安が軽減され、スムーズな本格復帰につながります2)。
実際、復職支援プログラムを受けた患者さんでは、受けていない患者さんと比べて復職後の継続率が高いこともわかっています(図)12)。図:復職支援プログラムを利用した患者さんと
そうでない患者さんの就労継続率の比較
- 復職支援プログラムではどんなことをするの?
-
復帰までに必要な能力を回復することを目的として、以下のようなことを行います2)。
オフィスワーク
パソコンを使った資料作成や、
会社を想定したロールプレイなどを行う。
グループワーク
他の参加者とディスカッションや
共同作業を行い、協調性を身につける。
運動
卓球やダンスなどのチームワークを必要と
するスポーツでは協調性も身につく。
心理教育
うつ病に関することや、うつ病患者さんの
社会復帰の方法などについて授業を受ける。
復職支援プログラムでは、患者さんは自宅から施設まで通勤と同じように通います(通所)。これはプログラムの一環であり、多くの場合、最初は週2日程度の通所から始め、徐々に日数を増やしていきます。患者さんの状態や希望によりますが、約半年ほど通所を続けます。
プログラムの内容や費用は施設ごとに異なりますが、内容に関わらず、うつ病の患者さんのグループで参加することが多いため、同じようにうつ病に苦しみ、職場復帰への不安をもつ仲間ができることは大きな力になるかもしれません。
- 自分でできる復職プログラムとは?
-
個人でできるリハビリや復職プログラムがあります。復職を目指したいのに近隣に通所型の施設がない患者さんや、どうしても施設を利用したくない患者さん、専業主婦の患者さん、まだ就業する予定のない患者さんは、以下の方法を医師と相談して試みてください10)。
 家事
家事- 掃除や洗濯、料理などは、ある程度の集中力や判断力を必要とします。家事には種類や段取りが多く、復職プログラムに代わるような作業がたくさんあります。また、家庭内の家事への負担が減り、実際の生活の質が向上することは、気分向上にもつながるでしょう。
 コミュニケーション
コミュニケーション- 休養や休職していることを打ち明けられる友人と食事に出かけるなど、意図的に家族以外の人と接する時間を作っていきましょう。ただし、人と話すことに過度な恐怖心を抱いてしまう場合は、無理をせず、外出時に出会った近所の人に挨拶をしたり、買い物の際に店員さんに「ありがとう」と声をかけたり、他人とちょっとしたやりとりをすることから始めてみるのがよいでしょう。
 通勤訓練
通勤訓練- 月曜日から金曜日にかけて、休職前の通勤の時間に合わせて起床・就寝するようにします。そして、通勤時と同じように身支度をして、通勤時と同じ方法で職場近くまで行きます。このプログラムでは、通勤による疲労感を確認できるだけではなく、職場へ近づくことへの不安や恐怖心なく通勤ができることを確かめることができます。
 模擬出勤
模擬出勤- 自分で1日や1週間のスケジュールを組み、出勤や作業、帰宅のシミュレーションを行います。たとえば「午前中は電車でジムへ行き、午後は図書館に行く」などです。この時、本や新聞を読んで要約やプレゼン資料を作成したり、パズルや単純な計算などを取り入れることで集中力を確かめましょう。ご自身の疲労感と相談しながら、時間の調整や場所の選定などを行うことが大切です。
 仕事に関する作業や勉強
仕事に関する作業や勉強- 急性期(うつ病治療中の過ごしかた)にあたる休職当初は、仕事に関することを遠ざけるようにしますが、このプログラムでは、復職間近になった段階で仕事に関する道具、制服、資料などを積極的に⽬にしたり⼿に取るようにします。この時、気分が悪くなることや動揺するようなことがあれば、復職の時期を再考するか、徐々に慣らすようにしていきましょう。慣れてくれば、パソコンなどを⽤いて簡単な作業をしてみてもよいでしょう。
- 家事
- 掃除や洗濯、料理などは、ある程度の集中力や判断力を必要とします。家事には種類や段取りが多く、復職プログラムに代わるような作業がたくさんあります。また、家庭内の家事への負担が減り、実際の生活の質が向上することは、気分向上にもつながるでしょう。

- コミュニケーション
- 休養や休職していることを打ち明けられる友人と食事に出かけるなど、意図的に家族以外の人と接する時間を作っていきましょう。ただし、人と話すことに過度な恐怖心を抱いてしまう場合は、無理をせず、外出時に出会った近所の人に挨拶をしたり、買い物の際に店員さんに「ありがとう」と声をかけたり、他人とちょっとしたやりとりをすることから始めてみるのがよいでしょう。

- 通勤訓練
- 月曜日から金曜日にかけて、休職前の通勤の時間に合わせて起床・就寝するようにします。そして、通勤時と同じように身支度をして、通勤時と同じ方法で職場近くまで行きます。このプログラムでは、通勤による疲労感を確認できるだけではなく、職場へ近づくことへの不安や恐怖心なく通勤ができることを確かめることができます。
- 模擬出勤
- 自分で1日や1週間のスケジュールを組み、出勤や作業、帰宅のシミュレーションを行います。たとえば「午前中は電車でジムへ行き、午後は図書館に行く」などです。この時、本や新聞を読んで要約やプレゼン資料を作成したり、パズルや単純な計算などを取り入れることで集中力を確かめましょう。ご自身の疲労感と相談しながら、時間の調整や場所の選定などを行うことが大切です。

- 仕事に関する作業や勉強
- 急性期(うつ病治療中の過ごしかた)にあたる休職当初は、仕事に関することを遠ざけるようにしますが、このプログラムでは、復職間近になった段階で仕事に関する道具、制服、資料などを積極的に⽬にしたり⼿に取るようにします。この時、気分が悪くなることや動揺するようなことがあれば、復職の時期を再考するか、徐々に慣らすようにしていきましょう。慣れてくれば、パソコンなどを⽤いて簡単な作業をしてみてもよいでしょう。

- 復職後数年がたち、自分がうつ病だったことを知らない同僚が増えてきた。
うつ病のことを明かした方がよいのだろうか? - とくに困っていないのなら、あえてうつ病だったことを伝える必要はないでしょう。
しかし、問題がないように思えても、昇進や転勤など、あらゆる出来事が病気の経過に影響する可能性があるため、復職後も復職支援プログラムを介してできた仲間との交流を保ち、日々の悩みを相談できる場をもっておくことが大切です11)。
【出典】
- 1)有馬秀晃 監修:うつ病の人に言っていいこと・いけないこと, 講談社, 東京, 2014
- 2)山本晴義 監修:図解やさしくわかる うつ病からの職場復帰, ナツメ社, 東京, 2015
- 3)日本うつ病学会 監修:うつ病治療ガイドライン 第2版, 医学書院, 東京, 2017
- 4)難波克行 著:うつ病・メンタルヘルス不調 職場復帰サポートブック, NextPublishing, 東京, 2017
- 5)厚生労働省ホームページ「こころの耳 ご存知ですか?うつ病 1 うつ病とは 」http://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad001/
- 6)Kupfer DJ:J Clin Psychiatry, 52 Suppl:28-34, 1991
- 7)野村総一郎 監修:図解やさしくわかる うつ病の症状と治療, ナツメ社, 東京, 2014
- 8)厚生労働省:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~, 平成25年11月
- 9)野村総一郎 監修:入門 うつ病のことがよくわかる本, 講談社, 東京, 2018
- 10)稲田泰之 監修:休職者のための復職マニュアル, ブックトリップ, 大阪, 2018
- 11)五十嵐良雄 監修:うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した人の気持ちがわかる本, 講談社, 東京, 2014
- 12)五十嵐良雄:日本労働研究雑誌 695(6):62-70, 2018
医療機関検索
ここから先は、厚生労働省が運営する
医療機関検索ページとなります。
移動しますか?
リンク先のウェブサイトは、武田薬品工業株式会社が運営するものではありません。
武田薬品工業株式会社はリンク先のウェブサイトの内容やサービスについて責任を負いかねます。
ご利用にあたっては、厚生労働省の規約をご確認ください。
うつとの向き合い方